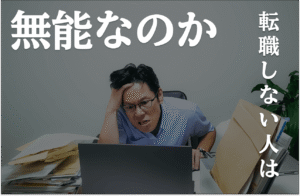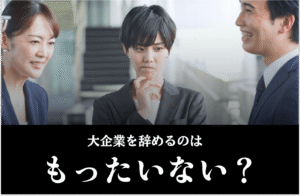「新卒で入社した会社をすぐに辞めたい」という悩みを抱えている方は、意外と多いです。
しかし、すぐに辞めてしまうと、キャリア形成や生活費の工面などで苦労する可能性があるため、なかなか退職に踏み切れないかもしれません。
今回は、新卒ですぐに辞めることを考えている方に向けて、新卒1年以内の離職率やすぐに辞めた人に待ち受けていることを解説します。退職後の行動パターンについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
新卒の1年以内の離職率
新卒1年以内に辞める人はどれくらいいるのでしょうか。
厚生労働省から、学歴別の離職率のデータが出ているのでみてみましょう。
出典:学歴別就職後3年以内離職率の推移|厚生労働省
上の棒グラフの黄色が1年目の退職、赤斜線が2年目の退職、白が3年目での退職割合を示しています。
大学卒の令和4年の数値を見ると、1年目で退職する人の割合は12.0%となっています。つまり、大卒の10人に1人は1年以内に退職していると考えられます。
また、令和2年の数値をみると、大卒で3年以内に退職している人は42.6%と、およそ半数近くにのぼります。
ちなみに、大卒と比べると、どの年でも高校卒、短大等卒のほうが1年目での離職率が高いことがわかります。
新卒ですぐ辞める人は意外と多い?
データを見ての通り、大卒の10人に1人は1年目に退職していることがわかります。
このような新卒の早期離職の背景には、企業側に責任があることもあります。
例えば、採用時の期待と現実のギャップや、適切なサポート体制が整っていないことが原因で、新卒社員が職場に適応できずに辞めるケースなどです。
最近では記憶に新しい、いなば食品の入社辞退者続出の件もこれに関係しています。主に、社宅に関する説明が実態と異なったことによる問題です。
そのため、新卒の早期離職は、個人の問題だけでなく、企業側の体制や環境の整備が求められる課題でもあるといえるでしょう。
参考:ホントのことが言えない企業はどうすれば? 「ちゅ~る」いなば食品騒動に学ぶ 社員採用に求められる姿勢|東京新聞
新卒ですぐ辞めなきゃ良かったと後悔している人はいる?
新卒で入社後すぐに辞めてしまったことを後悔する人は少なくありません。
まず、短期離職によって職務経歴が空白となり、次の転職活動で「なぜ辞めたのか?」と問われることがあります。また、新卒直後は生活にも余裕がなく、上京組であれば地方の実家に戻ったり、家賃が払えず借金をしたりする人もいるでしょう。
また、長期的には、スキルや経験の積み重ねが不足し、将来のキャリア形成に影響が出ることもあります。
さらに、職場に慣れる前に辞めてしまうことで、新しい環境で適応する力や忍耐力が養われず、同じような問題に再度直面する可能性も高くなります。
とはいえ、先ほどのいなば食品の例のように、企業側に問題がある場合は、無理に辛抱せず早めに見切りをつけることも大切だといえるでしょう。
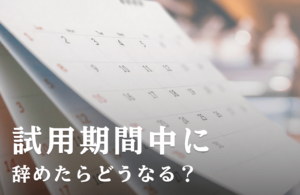
新卒ですぐ辞めたら「人生終わり」?
晴れて社会に出たのに、すぐ仕事を辞めてしまったことで「人生終わりだ」と考える人もいるでしょう。
しかし、1度の退職で人生が終わることなどありません。
特に新卒の場合、第二新卒としての転職枠が設けられていることが多く、再就職のチャンスは十分にあります。
大切なのは、次のステップで自分の強みや経験をどう活かすかです。早期に辞めたことを前向きに捉え、次に向けた行動を起こせば、いくらでも再スタートは可能です。
新卒ですぐ辞めた人にその後待ち受けていること
何も考えずに新卒ですぐに辞めてしまうと、さまざまな困難が待ち受けている可能性があります。新卒で早期退職した人がその後、どのようなことを経験しているのかを知っておくことは大切です。
ここからは、新卒で退職した後に待ち受けていることを解説します。
転職活動で不利になる部分がある
新卒で早期退職すると、転職活動で不利になる部分があります。企業は、採用した人材に長く働いてもらうことを期待しているため、短期離職する可能性がある人の採用に慎重になる傾向にあります。
また、明確な退職理由がないと、忍耐力や責任感、ストレス耐性がないと考えられてしまうかもしれません。
さらに、新卒1年目で辞めているため、社会人経験がほぼなく、社会人キャリアを駆使して転職活動できない点も、新卒ですぐに辞めることのデメリットです。

生活費に困る
新卒ですぐに辞めると、生活費の確保に苦労する可能性があります。転職活動中は、履歴書の作成や面接の準備などに時間をとられるため、アルバイトなどで収入を得るのも難しいことも考えられます。
貯金が底をつき、家賃や光熱費、食費などの支払いが滞ってしまうと、精神的なストレスも大きくなり、転職活動にも悪影響をおよぼすかもしれません。
健康保険料や年金の支払いが負担になる
社会人になると、健康保険料や年金の支払い義務が発生するため、負担が増大します。会社に勤めているときは、健康保険料や厚生年金保険料を、会社が一部を負担してくれます。しかし、退職してしまうと、すべて自己負担で支払わなければなりません。
退職後は、国民健康保険料や国民年金に加入する必要があります。無職でも、これらの支払いは免除されません。(一部、猶予される場合もあります)
国民健康保険は、前年度の所得に応じて支払う金額が決まり、毎月一定額の支払い義務が発生します。
また、国民年金は1カ月あたり約16,000円の支払いが必要です。未納期間があると、将来受け取れる年金額が減ったり、受給資格を得られなかったりすることもあります。
出典:国民年金保険料|日本年金機構
1人暮らしの場合は部屋を引き払わなくてはいけないことも
1人暮らしをしている場合、退職によって収入がなくなることで、家賃の支払いができずに部屋を引き払う必要が出てくるかもしれません。特に都市部で1人暮らしをしている場合は、家賃が高額になりますよね。
家賃の支払いが滞ると、大家から督促を受けたり、強制退去させられたりする可能性があります。新たな家を探す手間や費用が必要になり、転職活動に悪影響をおよぼすおそれもあるのです。
以上のことから、退職後の収入や支出をしっかり見直して、家賃をしっかり支払える体制を整えるべきです。
精神的に不安定になる
新卒で入った職場をすぐに辞めることで、精神的に不安定になる可能性があります。「なぜ仕事を続けられなかったのだろう」「これから生活できるのだろうか」と、自分自身に対する自信を失ったり、将来への不安が増したりするかもしれません。
孤独感や無力感から、食欲不振や睡眠障害、抑うつ状態に陥ってしまう可能性もあります。また精神的に不安定になると、転職活動も思うように進まなくなるかもしれません。
周りの人から心配される
新卒ですぐに辞めてしまうと、周りの人から心配されるかもしれません。家族や親戚、友人から、さまざまな言葉をかけられる可能性があります。「この先大丈夫なの?」「我慢が足りないのではないか」と言われて、強いプレッシャーやストレスを感じる人も多いです。
「新卒で辞めてしまうと、世間体が悪いのではないか」と気になり、精神的に不安定になることもあるでしょう。さらに、周囲の友人が順調に社会人生活を送っているのを見ると、自信を失うおそれがあります。
社会人経験がないので、今後のキャリアについて考えづらい
新卒ですぐに辞めてしまうと、社会人経験がほとんどないため、今後のキャリアプランを考えづらいと感じる人が多いでしょう。
2~3年社会人をやれば、ある程度自分の向き・不向きや「こんな仕事がしたい・したくない」がわかってきますが、新卒ですぐ辞めてしまうとその指標も見つけにくいです。今後どのようなスキルを身につければよいのかわからず、途方に暮れるかもしれません。
さらに、社会人としてのビジネスマナーや、コミュニケーションスキルが身についていない可能性があるため、キャリアを考えるうえで不安要素になりうるでしょう。
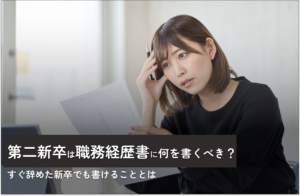
新卒入社から辞めるまでの期間によって、その後変わることはある?
新卒入社から辞めるまでの期間が長いほど、スキルアップの機会を得られる可能性が高いです。また、自分のやりたいことや得意なことを理解しやすいのも、長く働くことのメリットでしょう。
採用選考において、辞めるまでの期間が影響をおよぼす可能性はあります。しかし、在籍期間よりも退職理由のほうが、選考に与える影響は大きいといえます。退職までの期間にかかわらず、退職理由を明確にし、そこから得られた学びをアピールすることが大切です。
収入の確保手段として、失業保険の受給を考えている方もいるかもしれません。失業保険を受け取るには、以下に示す条件を満たす必要があります。
- ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること
新卒で1年未満に退職すると、失業保険を受け取れない点に注意しましょう。
出典: 基本手当について|ハローワークネットサービス
新卒ですぐ辞めたその後の行動パターン
新卒で退職した後の行動パターンは人それぞれです。計画的に行動することで、生活に困ることがなく次のステップに進めるでしょう。
ここからは、新卒ですぐ辞めたその後の3つのパターンを紹介します。
再就職のため転職活動を始める
新卒ですぐに退職した後、多くの人が再就職を目指して、転職活動を始めるでしょう。第二新卒を募集する会社は数多くあるため、自身のポテンシャルや仕事への意欲をアピールする転職活動がおすすめです。
面接時は、前職の退職理由を聞かれることがほとんどです。退職理由をポジティブに伝え、そこから得られた学びや成長を具体的に説明できるように、しっかり準備することが大切です。
また、自分の強みや弱み、興味のある分野などを自己分析し、どのような仕事が向いているかを知りましょう。転職サイトや転職エージェントなどを活用し、積極的に情報収集をおこない、自分に合った求人を探してくださいね。
職業訓練を受ける
新卒ですぐに退職した後、キャリアアップや希望する就職を実現するために、必要な職業スキルや知識を習得できる職業訓練(ハロートレーニング)を受けるのも、1つの方法です。
ハロートレーニングとは、失業保険がある人を対象とした「公共職業訓練」と、失業保険を受けられない人を対象とした「求職者支援訓練」との総称であり、仕事を探している人を対象とした公的な職業訓練制度です。
テキスト代を除いて無料で受けられるため、収入が途絶える間でも安心して利用できます。また、失業保険を受けられない人でも、一定の要件を満たせば、訓練受講中の生活費などが支給される制度もあります。
出典:ハロートレーニング(職業訓練)について|厚生労働省東京労働局
資格取得や特定のスキルを学べるスクールに通う
なかには、退職した後に、資格取得や特定のスキル習得を学べるスクールに通う人もいます。スクールに通うことで、体系的に知識を身につけられます。将来役立つスキルを身につけることで、転職の可能性を広げられるでしょう。
しかし、金銭面に余裕がない方は、心の安定のためにもできるだけ早く転職して、働きながらスクールに通うのがおすすめです。
新卒ですぐ辞めたその後の転職活動でのポイント
新卒ですぐ辞めた後の転職活動は、学生時代の就活とは勝手が異なります。
ここでは、少しでも内定を獲得できる可能性が上がるポイントを紹介します。
軽率に「どこでもいい」という気持ちで行動しない
新卒で短期離職した後に、再び「どこでもいい」という気持ちで転職活動を行うと、また同じ失敗を繰り返す可能性があります。
まず、なぜ短期離職に至ったのか、自己分析をするところから始めましょう。
また、企業分析も入念に行い、自分に合った企業を選ぶことが重要です。
適切な準備をしないまま転職すると、また同じような不満を感じ、再び短期離職するリスクが高まります。自分のキャリアビジョンを明確にし、慎重に次の職場を選びましょう。
第二新卒枠の求人に応募する
第二新卒枠の求人は、通常の中途採用枠と比べて、短期離職者に対して寛容といえます。企業側も、新卒者の柔軟性や適応力を期待しているため、短期離職の経験を大きなハンディキャップとは見なさないことが多いです。
特に、企業の教育プログラムが充実している場合、第二新卒枠での転職は、再びキャリアを築き直す良い機会となるでしょう。
面接用に適切な「退職理由」を考えておく
退職理由は、転職活動においてもっとも重要なポイントといえます。面接官に納得してもらえる、ポジティブで具体的な理由を用意しておく必要があります。
「職場が合わなかった」や「やりたいことが見つからなかった」といった曖昧な理由では、面接官にマイナスの印象を与えてしまいます。
自己分析を通じて、次の職場でどのように貢献できるかを考え、それに沿った退職理由を準備しましょう。
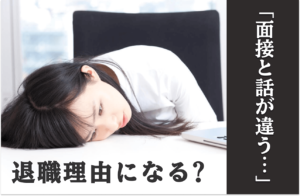
新卒ですぐ辞めたことにより満足している人もいる
新卒で早期に退職したことに満足している人も多く存在します。
特に、企業側に問題があり、職場の環境や人間関係に問題があった場合、早めに退職を決断したことが後々のキャリアにプラスになったと感じることもあります。
また、再就職した職場が自分に合っていたことで、仕事に対するモチベーションが向上し、生活全体が明るくなったという人もいます。
早めに行動することで、無駄なストレスを抱えずに次のステップに進めたというメリットを感じる人もいるので、短期離職した事実だけを悲観的にみるのはやめましょう。
新卒ですぐ辞めても転職できる◎
新卒の場合、すぐに辞めたとしても第二新卒枠の求人があるので、すんなり再就職できるケースも多く存在します。
あまり思いつめずに、次のアクションをとることで、納得のいく転職ができるはずですよ。
転職活動の進め方にはさまざまな方法がありますが、短期離職が原因でなかなか就職先が決まらないという人には、短期離職者向け転職サービスの「Zerobase」の利用をおすすめします。
Zerobaseに求人を掲載している企業は、短期離職者が求職者であることをあらかじめ認識しているので、短期離職の事実がネックになりにくいです。
通常の転職サイトや転職エージェントサービスで、なかなか内定がもらえないという方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。