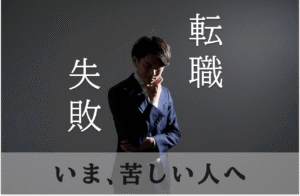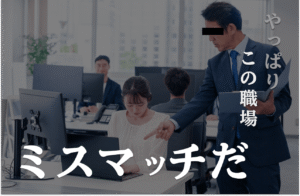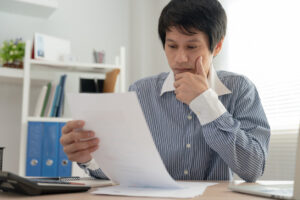「2回目か。もう終わったかもしれない」
そんな気持ちで、この記事を開いたのかもしれません。
20代で2度目の短期離職。たしかに、転職市場では厳しい目で見られる現実があります。しかし、まだ道は閉ざされていません。
今の状況を正しく整理し、自分の言葉で乗り越える準備をすれば、挽回は十分に可能です。
この記事では、20代で2回目の短期離職をした人が置かれている状況と向き合いながら、次の1歩をどう踏み出すかを一緒に考えていきます。
ぶっちゃけ、20代で2回目の短期離職はまずい?
「さすがに2回目はやばいかも」と不安になるかもしれませんが、今の時代、20代で転職経験が2回ある人は珍しくありません。マイナビの調査によると、20代の転職回数で最も多いのは「1回」(男性48.9%、女性57.3%)で、「2回」は男性31.3%、女性22.5%と続きます。
引用元:転職動向調査2024年版(2023年実績)|マイナビ
つまり、2回目までは一定のボリュームゾーンであり、極端に目立つわけではないということです。とはいえ、3回以上になると割合は9.5%(女性13.2%)と、一気に減少傾向にあり、人事からの印象も慎重になります。
また、このデータは短期離職に限った転職回数ではないので、その点は留意しておきましょう。
ネオマーケティングのデータによると、1年以内に自己都合で退職した会社での退職期間は、新卒入社の場合、半年以上1年以内が最も多くなっています。一方、中途では3カ月以内の22.6%が最も多く、見切りを付けるのは新卒よりも中途のほうが早いことが伺えます。
20代は、1度目の退職が新卒入社した会社、2度目が中途入社した会社であるケースがほとんどだと考えられるので、その2社で「いずれも1年未満で辞めた」となると、企業側から「また同じことになるのでは」と構えられる可能性は高まります。
とくに中途採用では、即戦力としての期待値が高いため、3カ月や半年での退職は“採用の見込み違い”と受け取られやすい側面もあります。
参考:新卒入社した会社よりも中途入社した会社の方が、退職の判断がより早い|株式会社ネオマーケティング
20代で2回の短期離職をした人への企業の印象は?
20代で2回目の短期離職となると、「さすがに印象は悪いのでは」と感じる人も多いかもしれません。実際、企業側がどのように見ているのでしょうか。
dodaの調査によれば、「転職回数が選考に影響しないのは何回までか」という問いに対し、20代では「3回目から気になる」が28.2%、「2回目から気になる」が22.3%という結果でした。
つまり、2回目の時点で気にされることも少なくない、というのが現実です。
一方で、30代や40代では「回数は関係ない」が最多となっており、年齢が上がるほど転職回数に対する見方はやわらかくなる傾向にあります。
とはいえ、20代でも「やりたいことを見つける途中だから」「納得できる理由があれば問題ない」といった前向きな捉え方をする企業も存在します。
短期離職が2回あることよりも、その理由をどう説明し、次にどうつなげるか。採用担当者は、そこを注視しているのです。
参考:転職回数が多いと選考結果に影響がある?採用担当者の印象や対策方法を解説 |dоda
20代で2回目の短期離職をした人に待ち受けていること
2回目の短期離職をした後、気持ちを切り替えて次の職場を探そうと思っても、現実はそれほど甘くないかもしれません。履歴書の段階で落とされる、面接で退職理由を深掘りされる、応募できる求人が減る……。そんな壁にぶつかる人も多くいます。
ここでは、2度目の短期離職後に起きやすいリアルな変化や課題について、具体例を交えながら解説していきます。

次の転職で“本気度”を疑われやすくなる
企業の採用担当者は、応募者の経歴を見て「この人は続けられるか」を慎重に判断します。
2回連続で短期間での離職があると、たとえそれぞれに理由があっても、「今回もすぐに辞めるのでは」と疑われやすくなります。
たとえば、「人間関係が合わなかった」「想像と違った」といった理由は、それが事実であっても説得力を持たせるのが難しいです。
転職理由を問われたとき、「なぜ合わなかったのか」「次は何を重視して選んでいるのか」を自分の言葉で説明できなければ、面接突破は厳しくなるでしょう。
「辞め癖」がつくリスクがある
短期離職を2回経験すると、「限界を感じたら辞める」という判断が無意識に定着してしまうことがあります。もちろん、辞めること自体が悪いわけではありません。問題は、その判断が“早すぎる”ことに自分でも気づけなくなる点です。
ある20代の男性は、2社続けて半年以内に退職。「もう少し我慢できたかもしれない」と後から振り返ることができた一方、次の職場でも小さな違和感に過敏になり、早期離職のループに入りかけていました。
“辞め癖”はキャリアのリズムを崩しやすいため、気づいた段階で立ち止まり、次は「何が許容できて、何が耐えられないのか」を見つめ直すことが大切です。
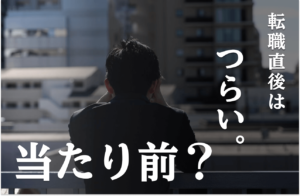
焦りと自己肯定感の低下でメンタルが不安定に
同年代の友人が安定して働き始めている一方で、自分だけが職場を転々としている。
そんな状況になると、「自分は社会人としてダメなんじゃないか」という感情が湧いてくることもあるでしょう。
とくに2回目の離職後は、応募してもなかなか選考が通らず、就職活動が長引くケースも多く見られます。焦る気持ちが強まると、条件を深く見極める余裕がなくなり、またミスマッチな企業を選んでしまうリスクも高まります。
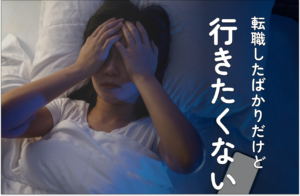
失業保険が出ない/出てもすぐ切れる可能性がある
「辞めた後、しばらくは失業保険でなんとかなるだろう」と思っている人もいますが、条件によってはそもそももらえないこともあります。
原則として、失業保険の受給には「直近2年間で12カ月以上、雇用保険に加入していた」ことが必要です。たとえば、1社目が半年、2社目が3カ月といった場合、受給資格を満たしていない可能性があります。
仮に受給できたとしても、支給期間は通常90日間。転職活動が思った以上に長引けば、あっという間に生活が不安定になります。
退職後の数カ月を見据えた備えがなければ、精神的にも金銭的にも追い込まれかねません。
20代で2回目の短期離職をする人にありがちな特徴
2回目の短期離職をした人の話を聞いていくと、「ああ、自分にも心当たりがあるかも」と感じる共通点がいくつか見えてきます。
これは決して誰かを責めるためではなく、次の選択で同じことを繰り返さないための“ヒント”として見ておきたいポイントです。
企業選びが表面的になっている
求人サイトで見つけた「土日休み・残業少なめ・アットホーム」などの言葉に惹かれ、そのまま応募したことはありませんか?
条件やイメージだけで企業を選んでしまうと、入社後に「こんなはずじゃなかった」とギャップを感じやすくなります。
たとえば、前職では「裁量が大きい」と書いてあったのに、実際はマニュアル通りの業務ばかりでやりがいを見出せなかった……。そんな声もよく耳にします。
企業選びにおいては、具体的な仕事内容・組織の雰囲気・評価のされ方など、深掘りした情報収集が不可欠です。
自分の価値観や働き方の軸が定まっていない
「自分がどんな仕事に向いているか」「どんな環境でなら続けられそうか」といった価値観が曖昧なまま転職活動をすると、毎回“当てずっぽう”のような選び方になりがちです。
- 「なんとなく営業職は活発そうで合うと思った」→「実際は数字に追われてしんどかった」
- 「福利厚生が手厚い会社なら安定すると思った」→「制度はあるけれど、結局活かせる風土じゃなかった」
こういったズレは、価値観と仕事内容が噛み合っていない証拠です。
短期離職を繰り返す人の多くは、「自分の働き方の軸」が明確にならないまま走り出してしまっている傾向があります。
入社後に“辞める選択”への心理的ハードルが下がっている
1度でも短期間で辞めた経験があると、2回目は想像以上に「辞める」という判断が早くなりがちです。
「前も辞めたし、また辞めてもなんとかなるだろう」という気持ちがどこかにあると、小さな違和感やストレスに過敏に反応してしまうことがあります。
もちろん、無理して続ける必要はありませんが、「今回は前回と何が違うのか」「今の悩みは、辞めずに解決できるものなのか」と1度立ち止まって考える時間を持つ必要があります。
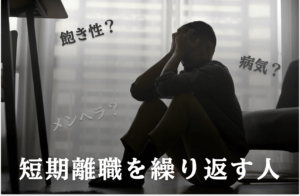
【回数別】20代で2回以上短期離職している人の置かれている状況
短期離職が2回を超えると、転職市場での見られ方は徐々に変わっていきます。採用担当者は、履歴書の“転職回数”だけでなく、“在籍期間”にも目を光らせており、「短期間での離職が複数ある=安定して働けない人かもしれない」と考える傾向が強くなります。
ここでは、回数別にどう見られやすいかを整理します。
3回目
20代で3回目の短期離職となると、企業側は「そもそも職場に適応する力が弱いのでは」「また同じことを繰り返すのでは」と一層慎重になります。
たとえば、3社とも在籍が1年未満であれば、いくら個別に理由があっても、「何か本人側にも原因があるのでは」と捉えられやすくなります。
とはいえ、3回目の段階であれば、キャリアの立て直しはまだ十分可能です。
「自分の価値観をようやく言語化できた」「今度こそミスマッチを避けたい」といった意志と行動が見える人は、ポテンシャルを評価されることもあります。
4回目
ここまで来ると、企業からの印象はかなりシビアになります。「続ける努力をしてこなかったのでは?」「職場に対して不満ばかり持っているタイプかも」と疑念を抱かれやすく、応募できる求人も一気に狭まります。
また、書類選考すら通らないという声も増えてくる段階です。
この状況では、“今後どうしたいか”に加え、“なぜ4回続いたのか”についての説明が求められます。選考では、キャリアコンサルタントのサポートを受けながら応募書類をブラッシュアップするなど、戦略的に動く必要が出てきます。
5回目
20代で5回の短期離職となると、いわゆる「離職歴の多い人材」としてレッテルを貼られてしまうリスクが高まります。
1部のベンチャー企業や経験者採用枠を除けば、正社員登用の選考ハードルは非常に高くなるのが現実です。
その一方で、焦って応募先を広げすぎると、また同じようなミスマッチに陥りかねません。
この段階では、1度立ち止まって「職種選びから見直す」「働き方そのものを考え直す」など、キャリアの軸を根本から整理することが必須です。
【FAQ】20代で短期離職を2回以上している人によくある質問
20代で複数回短期離職している人が疑問に感じやすいポイントに触れます。
2回目の短期離職は20代後半のほうがまだマシ?
一概に「後半だから有利」というわけではありませんが、20代前半よりも「ある程度社会経験を積んだうえでの判断」と受け取られやすい面はあります。
とはいえ、20代後半になると「そろそろ腰を据えて働きたい」という企業の期待も高まるため、「今後どう働いていきたいか」を具体的に語れる必要があります。
30代と20代では企業の印象も異なる?
はい、異なります。先述のdodaの調査によれば、30代以上では「転職回数は関係ない」と考える採用担当者が最も多い一方で、20代では「2回目から気になる」「3回目から気になる」といった慎重な見方が目立ちます。
20代はまだ“土台を築く時期”と見なされる分、短期離職の印象が強く残りやすいことを意識しておきましょう。
20代で2回短期離職をした人の転職時の注意点・心構え
2回の短期離職がある場合、次の転職は「選び方」と「伝え方」が運命を左右します。
企業側も慎重に見てくるからこそ、自分自身もこれまで以上に冷静で具体的な準備が必要です。
退職理由を「納得感のある言葉」で説明できるようにする
短期離職が続いている場合、採用担当者はまず「なぜ辞めたのか」に注目します。ここで避けたいのは、「なんとなく合わなかった」「忙しくてつらかった」などの曖昧な表現です。
たとえば、「営業職を選んだが、実際は新規飛び込み中心で、自分の特性と大きくズレていた」といったように、仕事内容・環境・自分の特性とのギャップを冷静に言語化することが大切です。
そして「だから次は○○を重視して探している」とつなげることで、単なる言い訳ではなく、学びとして受け取ってもらいやすくなります。
企業選びは“譲れない条件”を絞って進める
2回の離職を経験したからこそ、「今度こそ長く続けたい」と思うはず。そのためには、自分にとっての“譲れない条件”を明確にすることが重要です。
たとえば、「数字よりも人とじっくり関わる仕事がしたい」「成果よりプロセスを評価してくれる文化が合う」など、これまでの職場で感じた違和感を反転させた視点で、軸を洗い出してみましょう。
条件を広げすぎるとまたミスマッチが起きやすくなるため、優先順位をつけて企業選びをすることが、結果的に自分を守ることにもつながります。
「次こそ定着したい」という意志を明確に伝える
転職回数よりも、「この人は次を最後にしたいと思っているか」が伝わるかどうかが、選考では重視されます。
「同じことを繰り返したくない」という気持ちは、採用側にも伝わるものです。
面接では、「これまでの経験から自分に合う環境が見えてきた」「この会社ではそれが満たされると感じた」といった前向きな理由と定着への意志をしっかり言葉にしましょう。
言い方1つで、「また辞めそうな人」ではなく、「経験を通じて軸が見えてきた人」として見られるようになります。
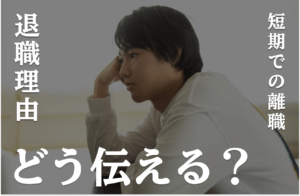
20代なら短期離職を繰り返しても可能性は十分
20代での短期離職は、たしかに企業から厳しい目で見られることもあります。
ただ、それでも20代には「まだ伸びしろがある」「環境を変えて再出発できる」という大きなアドバンテージがあります。家族やローンといった重い責任を背負っていない人も多く、方向転換やチャレンジがしやすいのも、この年代ならではです。
とはいえ、一般的な転職市場では短期離職の経歴が選考のハードルになる場面もあります。
そんなときは、短期離職者向けの専門サービス「Zerobase」を活用するのも1つの手。Zerobaseには短期離職に理解のある企業だけが登録しており、これまでの経歴にとらわれず、自分らしく向き合える企業と出会える環境が整っています。
我々は短期離職からの再起を「Zターン」と呼んでいます。「ミスマッチを感じて短期離職する=1度引き返す」ことで、本当に自分に合った環境が見つけられる可能性は十分にあります。
今や終身雇用の時代ではありません。あなたらしさに価値を感じてくれる環境が必ず見つかるはずです。