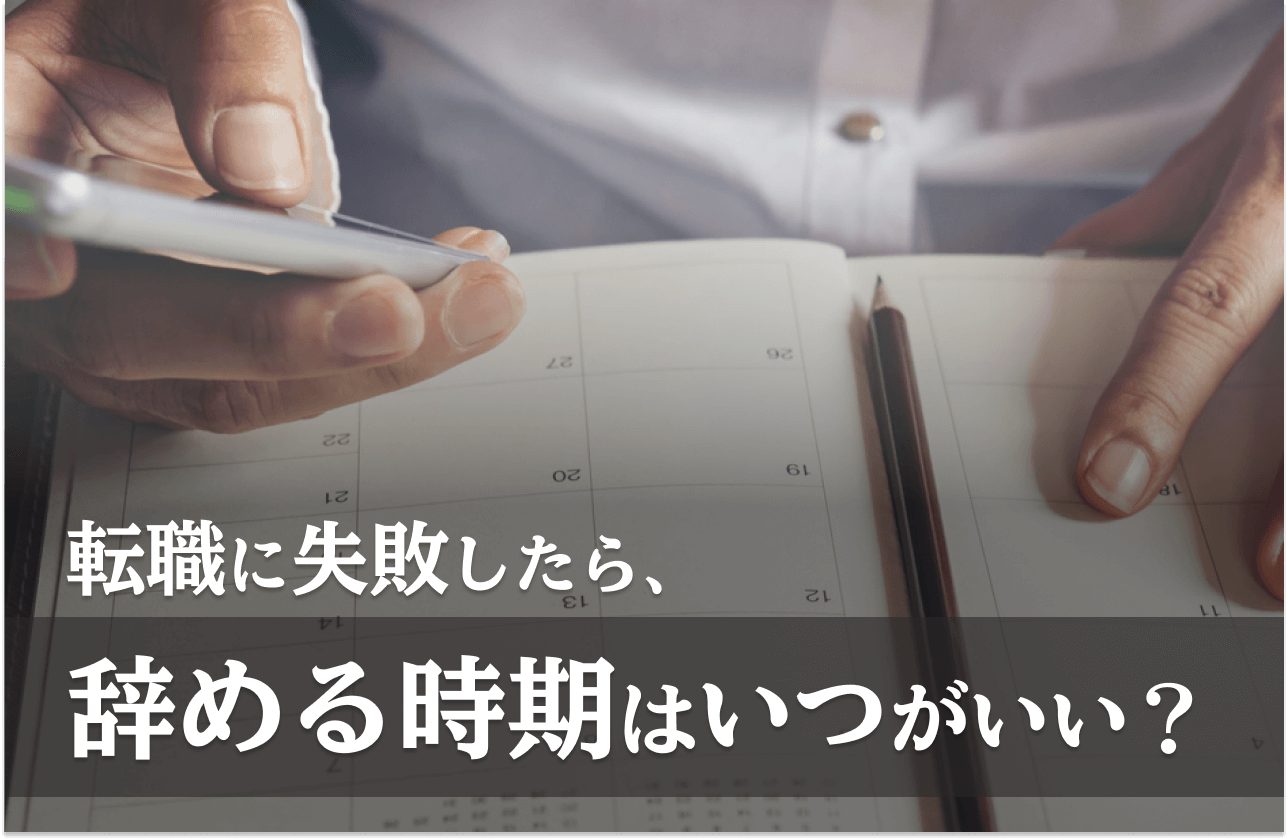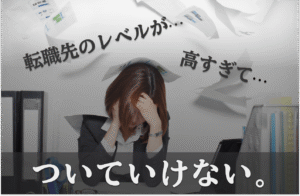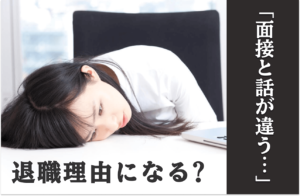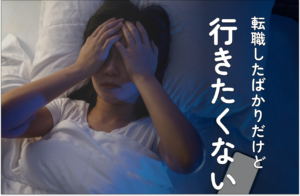転職後、仕事内容や職場の雰囲気に違和感を覚え、早期退職を検討するケースは少なくありません。しかし「すぐ辞めると不利なのでは」「どのタイミングが損しないのか」と判断に迷う人も多いはずです。
転職に失敗したとき、辞める時期によってどのような違いがあるのか。本記事では、その見極め方や影響について整理していきます。
転職に失敗した人が辞める時期の平均は?
引用元:採用支援ツール『engage』中途入社者の定着に関する調査レポート|エン・ジャパン
採用支援サービス「engage」を運営するエン・ジャパンの調査では、中途入社者がもっとも退職しやすいタイミングは「入社から3カ月未満」とされています。
内訳を見ると、「1カ月未満」が8%、「1カ月以上3カ月未満」が26%。あわせて3割以上が、入社から3カ月以内に職場を離れていることになります。
これは入社後すぐに、仕事内容や職場の雰囲気にギャップを感じてしまい、早い段階で見切りをつけるケースが多いと考えられます。なかでも大企業ではこの傾向が強く、短期間での離職が目立つ結果となっています。
さらに「1年未満」まで広げると、全体の約7割が該当しており、中途入社において1年以内の退職はめずらしくない実態が見えてきます。
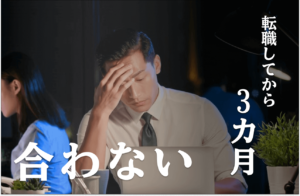
転職に失敗してから辞めるまでの時期(期間)による影響の違い
転職後、「この職場ちょっと違うかも」と感じても、すぐに辞めていいのか、それとも少し様子を見るべきかは悩みどころ。実は、辞めるタイミングによって、再転職のしやすさや制度の扱いに違いが出てきます。
ここでは在籍期間ごとの違いをざっくり見ていきましょう。
1カ月未満
ほぼ何もしていない状態での退職。職務経歴として扱われないこともあり、面接での説明も難易度はかなり高めです。
また、雇用保険の加入期間も足りないため失業手当の対象にもなりません。気持ち的にはすぐ抜けたくても、社会的には“辞めた感”すら残らない立ち位置になります。
1カ月
在籍の記録は残るものの、実績として語れる内容はほとんどありません。面接では「なぜ1カ月で辞めたのか」を必ず聞かれるため、理由の整理は必須。
制度面では、健康保険や住民税の切り替えなど、最低限の事務手続きが出てくる段階です。
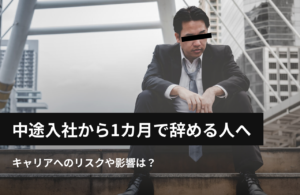
3カ月
試用期間の終わりに差しかかる時期です。企業側も“見極めの期間”と考えているため、やむを得ない事情があれば比較的理解を得やすいタイミングです。
失業手当の受給条件(原則12カ月)には届きませんが、次の職場探しで大きなハンデにはなりにくくなってきます。
6カ月
いわゆる「短期離職」として扱われがちな境目が6カ月です。ここまで働けば、それなりに実務に携わった印象を持たれやすく、転職活動での説明もしやすくなるでしょう。
雇用保険の受給資格を満たす可能性も高くなり、金銭面の不安がやや減るのもこのあたりです。
1年
1年在籍していれば、「すぐ辞めた人」という印象はかなり薄まります。職務経歴としてもしっかりカウントされ履歴書の見え方も安定してきます。制度的にも、失業手当や退職金(制度があれば)などに関わるラインです。
ただし1年ごとに転職を繰り返している場合は注意が必要です。1回だけなら理解を得られても、何度も続くと「またすぐ辞めるかも」と警戒されやすくなります。
職歴全体の印象として“落ち着きがない”と見なされないよう、説明できる理由や一貫した軸を持っておくことが大切です。
転職失敗後、辞める時期が早いことによるデメリット
転職後すぐに辞めると、次の転職活動に響いたり生活面でも思わぬ負担が生じたりすることがあります。
ここでは、早期退職によって生まれやすいデメリットをみていきましょう。
履歴書に傷がつきやすい
たとえば「1カ月で退職」といった職歴があると、面接官からは「なぜそんなに早く辞めたのか?」と突っ込まれやすくなります。1回ならまだしも、短期離職が複数あると「またすぐ辞めるのでは」と警戒される可能性も……。
特に正社員として働いていた場合は、たとえ短期間でも履歴書に省略しにくく経歴として残りやすいのが実情です。
再転職時の選択肢が狭まる
企業側が重視するのは「安定して働いてくれるかどうか」。そのため、早期退職の履歴があると書類選考の段階で落とされることもあります。
たとえば「入社1カ月で退職した人」と「3年間勤めた人」が並んだ場合、後者のほうが安定性を期待されやすいのは明らかです。結果として、応募できる求人の幅が狭まったり選べる業種・職種が限られたりすることにもつながります。

職務経歴としてアピールしにくい
職務経歴書に書けるような実績や成果がないまま辞めてしまうと、「この会社で何をしていたのか」が説明しづらくなります。
たとえば、入社後すぐに研修だけ受けて辞めたというケースでは、実務経験がゼロに近いため書類上の説得力が弱くなります。
短期であっても「何を感じて、どう動いたのか」を整理しておかないと面接でも話が浅くなりがちです。
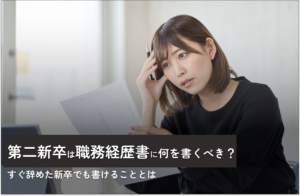
金銭的・精神的な負担が増える
すぐに辞めると、次の職が決まるまでの収入が断たれます。失業手当も原則として「雇用保険に12カ月以上加入」が条件のため、在籍期間が短いと対象外です。
貯金の取り崩しや親族への頼りが必要になることもあるでしょう。
また、精神的にも「また失敗するのでは」「早く決めないと生活が厳しい」と焦りが出やすくなり、余裕のない状態で再転職に踏み切ってしまうケースが少なくありません。
転職失敗後、辞める時期を遅らせるデメリットもある?
早く辞めることにはさまざまなマイナス面がある一方、「もう少し頑張れば慣れるかも」と踏みとどまった結果、逆に状況が悪化してしまうこともあります。
たとえば、職場で強いストレスを抱えたまま働き続け心身に不調をきたすケース。メンタルを崩して休職や通院が必要になると、退職の判断が遅れたぶんだけ再スタートにも時間がかかります。
また、「声をかけてもらっていた会社に乗っておけばよかった」と後悔する場面もあります。次のチャンスが目の前にあるのに、「まだ辞める決心がつかない」と先送りにしてしまうと、流れを逃してしまうことに。
我慢しても状況が変わらない場合は、辞める勇気も冷静に検討する価値があります。
転職に失敗した場合、辞める時期の決め方は?
勢いで動くと後悔することもありますが、我慢しすぎてもリスクがあります。
ここでは、辞める時期を考えるうえで押さえておきたい判断の軸を紹介します。
「辞めたい理由」が一時的かどうかを見極める
まず、その違和感がずっと続くものか、一時的なものかを見極めることが大切です。
たとえば、入社直後の繁忙期に「仕事が多すぎる」と感じても、季節要因で落ち着くこともあります。また、相性の悪い上司が異動する予定があるなら、急いで辞める判断は早いかもしれません。
短期間で状況が変わる可能性があるなら少し待つ選択肢もあります。
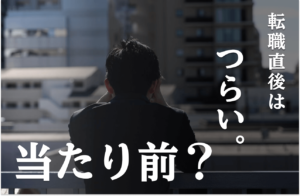
心身への影響を客観的に確認する
気づかないうちに無理を重ねていることもあります。
たとえば「夜眠れない日が続いている」「日曜の夕方に動悸がする」など、体や心にサインが出ているなら注意が必要です。医師の診断が出るレベルに達していなくても、日常生活に支障が出ているなら、タイミングにかかわらず退職を検討すべきでしょう。
「次の転職にどう響くか」から逆算する
辞める時期は、その後の再転職活動にも影響します。
たとえば1カ月で辞めると、職務経歴としてアピールできる内容が乏しく、選考時に不利になることがあります。一方で、3〜6カ月ほど在籍していれば、「なぜ辞めたのか」を整理すれば説明の余地はあります。
どのくらい働いたかによって、次に応募できる企業や職種の選択肢も変わってくるため、先を見据えて判断する視点をもっておきましょう。
制度・契約・金銭の影響から判断する
たとえば、雇用保険の失業手当を受けるには原則として12カ月以上の加入期間が必要です。まだ満たしていないなら、もう少しだけ在籍して条件をクリアしてから退職するという考え方もあります。
また、賞与や退職金の支給条件が「在籍半年以上」などになっている場合、そのタイミングを過ぎてから辞めることで損せず済むケースもあります。
転職先を辞めるのに適した時期(タイミング)はある?
転職に失敗したと感じたとき、辞めるタイミングに“絶対の正解”はありません。ただし、辞めたい理由や心身の状態、次の転職活動のことなど複数の視点をもとに整理すれば、自分にとってベストな判断がしやすくなります。
辞めるか迷ったときこそ、勢いだけで動かず、一度立ち止まって考えることが、結果的に最短のリスタートにつながることもあります。
タイミングは「探す」のではなく、「自分でつくる」という視点も大切です。
【年代別】転職後、辞める時期が早いことによる影響
同じ短期離職でも転職市場における見られ方や再スタートの難しさは年代ごとに変わってきます。30代~50代における違いをみていきましょう。
30代
まだ若手〜中堅として扱われる年代であり、ポテンシャルや柔軟性に期待されることが多い時期です。短期離職があっても「キャリアの試行錯誤の段階」と受け止めてもらいやすく、転職のやり直しは比較的しやすい傾向があります。
ただし、30代後半に差しかかってくると即戦力性が重視されるため、1年未満の離職が続くと「職場適応力に不安があるのでは」と見られる可能性も出てくるでしょう。

40代
マネジメント経験や専門性が求められる層に入ってくるため、短期離職があると企業側も慎重になります。「即戦力として迎えたのにすぐ辞めた」という印象が残ると、再転職の際に評価が厳しくなることがあります。
また、40代は求人自体が30代に比べて少なく、選択肢も狭まりやすい年代です。仮に退職を選ぶ場合は、「どの会社でも通用するスキルや実績があるか」を整理したうえで、計画的に動く必要があります。
50代
転職市場ではさらに狭き門となり、短期離職の影響も重く受け止められやすくなります。特に50代の場合、求人数が少ないうえに「すぐ辞めた=組織にフィットしにくい」という見られ方をされやすく、再転職のハードルが一気に上がります。
一方で、豊富な経験や人脈を活かして独立やフリーランスなど別の道を模索する人も増えてくる時期です。辞めたあとに何を軸にするかを明確にしておくことが、次の選択肢を広げる鍵になるでしょう。
再転職では、辞めた時期より辞めた理由が重要
短期離職という事実があっても、採用担当者が本当に知りたいのは「なぜ辞めたのか」「何を得て、どう立て直そうとしているのか」です。理由に納得感があれば、その先にあるポテンシャルや意欲を評価してもらえることもあります。
とはいえ実際には、「1年未満で辞めた」という経歴だけで書類選考で落とされるケースも少なくありません。一般的な転職サイトやエージェントでは、短期離職の背景に目を向けてもらえず、再チャレンジが難航することもあります。
そんな方におすすめしたいのが短期離職者に特化した転職支援サービス「Zerobase(ゼロベース)」です。企業側も最初から短期離職を前提にした選考姿勢を持っており、経歴ではなく「これから」にフォーカスしたマッチングが可能です。
また、Zerobaseのマッチ度診断では、給与や福利厚生などの決まった条件ではなく、企業文化や職場の雰囲気など、日々働くうえで重要な“真の相性”が良い会社とのマッチを期待できるので、再転職先とミスマッチする可能性も下げられるでしょう。
Zerobaseと掲載企業は、本気で再転職したい短期離職者をお待ちしております。